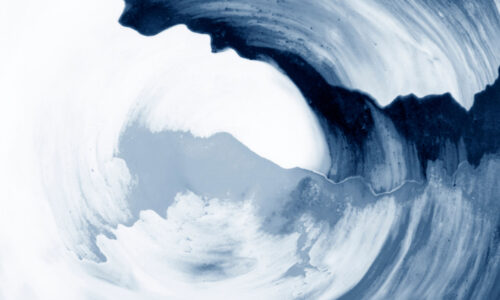
吉本ばなな連載『和みの想い出』第1回
2020.02.14 COLUMN
亡き父はよく日本茶を飲む人だった。
そしてどんなにお金がないときでも、お茶の質を落とすことはなかった。いつも決まったお店の決まったお茶だった。最高級ではないが、いい煎茶を買っていた。
父が急な坂道を降りてお茶を買いに行く様子は今でも目に浮かぶ。今はもうない、小さなお店だった。
日本茶、大学いも、コロッケと3つのおいしいお店が囲んでいるそのゴールデントライアングル(?)に散歩に行くことを父は心の拠りどころにしていたんだろう。
ものを書く仕事をしているとよくわかる。おやつが食べたいわけじゃない、小さな区切り、きらっと光るごほうびがあるからそこまでの時間をがんばれたんだろうなということが。
「君の淹れるお茶はおいしいなあ、さすが茶道部」とよく父に言われたのだが、茶道部では煎茶は淹れない。私がお茶を淹れるのがうまい理由は日本茶喫茶でアルバイトをしていたからである。
でもそう言われると嬉しかった。たくさんお茶を淹れたことが身についているんだなと思うからだ。
お茶を淹れるということは、「待てる」ということなのだ。
全てを一拍くらい遅くする。コーヒーとは違う。「あ、忘れてた」くらいの気持ちがないとおいしくならない。
お湯が沸くのも、お湯を冷ますのも、お茶の葉が開くのも、目の前で計りながらじりじり待つとよろしくない。ちょっと目を離したり他のことをしながらお茶の様子を見ているくらいの感じがせっかちな私にはちょうどいい。
切れが必要なのは最後に急須をぴしっと振って、いちばんおいしい急須の中の最後の一滴をしぼりだすときくらいだ。この一滴の中においしい味がみんな詰まっている。ただそれだけ。
その全部のこつを集めるときっと「心」と呼ばれるニュアンスが生まれるのだろう。
父が亡くなってから、実家の台所でほんとうにおいしいお茶をなかなか淹れられなくなった。なぜかわからない。たぶん、最後の数年は「今日淹れるこのお茶が父に淹れる最後のお茶かもしれない」と思って気合が入っていたからだと思う。それが抜けてしまったのだろう。
それでも同じ場所で同じようにお湯を沸かしていると、なにかが蘇ってくる。茶葉の声みたいなものが。
それはいつも「そろそろだよ」みたいな優しい声で、決して急かしたり強いたりしない。
実家の台所は改装して当時と少し変わってしまったけれど、動きは同じ。お湯がちんちんに湧いて吹きださんばかりになっているところから、湯飲みに温め用のお湯を注いでちょっとだけ待つ。
「これ以上冷めたらだめだよ」と急須の中のお茶が言う。
それを感じてから初めてやかんのお湯をほんの数滴、急須に注ぐ。蒸らす感じでひと呼吸置いて、次にわりと勢いよくお湯を足す。玉露でもないかぎり、わりと熱いうちにドバッと入れて大丈夫。そして湯飲みの中の湯を残らないようによく切ること。
あとは茶が呼ぶのを待つ。
ただそれだけ。どんなに忙しくてもそのときだけは、焦らない人でいたい。
吉本ばなな
1964年東京都出身。1987年『キッチン』で海燕新人文学賞を受賞し作家デビューを果たすと、以後数々のヒット作を発表。諸作品は海外30数ヶ国以上で翻訳、出版されており、国内に留まらず海外からも高い人気を集めている。近著に『切なくそして幸せな、タピオカの夢』『吹上奇譚 第二話 どんぶり』など。noteにて配信中のメルマガ「どくだみちゃんとふしばな」をまとめた文庫本も発売中。
note.com/d_f (note)
twitter.com/y_banana (Twitter)

2025.05.23 INTERVIEW日本茶、再発見

2025.03.07 INTERVIEW茶のつくり手たち

2025.03.21 INTERVIEW日本茶、再発見

2024.09.20 INTERVIEW茶のつくり手たち

2024.10.11 INTERVIEWCHAGOCORO TALK

2025.01.03 INTERVIEW日本茶、再発見茶と食

内容:フルセット(グラス3種、急須、茶漉し)
タイプ:茶器

内容:スリーブ×1種(素材 ポリエステル 100%)
タイプ:カスタムツール